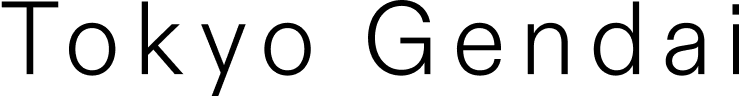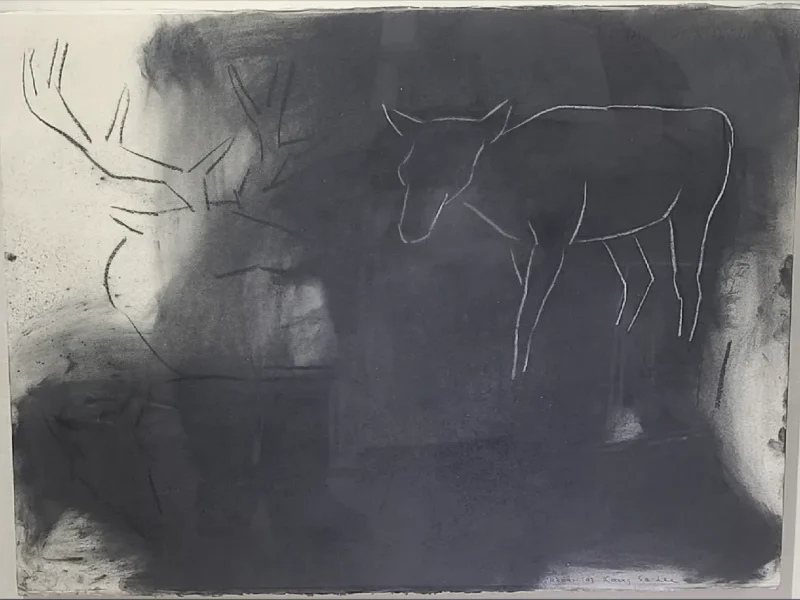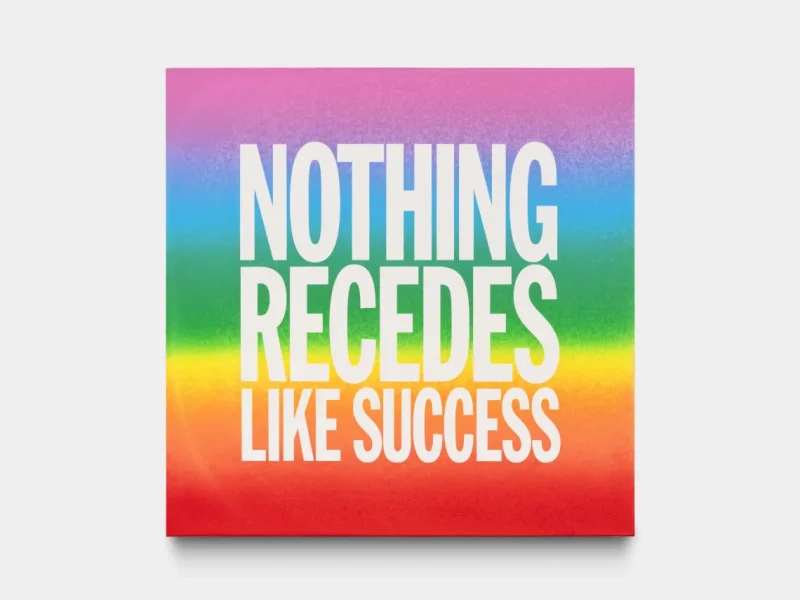執筆:Melanie Gerlis
アート市場ジャーナリスト、著述家
翻訳:Tokyo Gendai 編集部
多くの国において、2024年のアート市場は低迷の年だった。「The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2025」レポートによれば、世界全体の売上は12%の減少となった。主要な市場である米国で9%、中国で31%とそれぞれ落ち込む中、例外であったのが日本だった。日本市場では、全体で前年比2%増、特にギャラリー部門は7%増と、際立った成長を見せた。
Arts Economicsの創設者でありこのレポートを作成したClare McAndrew氏は、「特に日本は、昨年、明るい材料がいくつかありました。政府が市場活性化を全面的に後押ししているのです。」と述べる。
こうした取り組みは着実に成果を上げている。日本には文化と収集の長い歴史がある一方で、現代アート市場にも新たなエネルギーが宿り始めている。「30年前とはまるで別物です」と語るのは、1994年に東京でタカ・イシイギャラリーを始めた東京出身の石井 孝之氏。国際的なアート・シーンでもおなじみの存在となった氏が今、力を注いているのが次世代のギャラリスト育成だ。昨年、氏は小山登美夫ギャラリー、そしてかつてのスタッフでもある若い二人が立ち上げたKOSAKU KANECHIKA(2017年設立)、Yutaka Kikutake Gallery(2015年設立)と協力し、東京・京橋のTODA BUILDINGに新たなギャラリー施設を創設した。
今年9月に第3回を迎えるアートフェア 「Tokyo Gendai」 のフェアディレクターである高根 枝里氏は「こうした協業の精神こそ、日本のアート・シーンの特徴です。」と指摘する。「私たちは互いに助け合いますし、個人主義よりも集団主義を重視するアジア的な考え方が根付いていると思います。」と語る。Tokyo Gendaiは、日本国内外でのパートナーシップに重点を置き、今年は同時期に開催される国際芸術祭「あいち2025」とも連携する。さらにTokyo Gendaiは韓国との連携も強化する。韓国のアートフェア「Art Busan」との新たな提携のひとつのかたちとして今回のTokyo Gendaiに韓国から10のギャラリーを招待するとともに、Tokyo Gendai開催期間自体を4回目を迎える 「Frieze Seoul」 の翌週となる9月第2週に設定した。
西欧のギャラリーも活況を呈す日本のアート・シーンに注目している。昨年にはPace Galleryが麻布台ヒルズにオープンし、麻布台ヒルズギャラリーとの共催で開催されたAlexander Calder氏の大規模個展でも注目を集めた。今年も、5月にはCeysson & Bénétière のアジア初となる拠点を銀座に開設するなど国際的な動きがある。東京に常設スペースを開設する決定を行ったCeysson & Bénétièreのギャラリーディレクター Loïc Garrier氏は「Tokyo Gendaiには開催から2回とも出展し、日本だけでなく、韓国、シンガポール、台湾、中国からもしっかりと購入がありました。我々にとって、東京はまさにアジアのハブなのです」と語る。
石井氏は、現在の国内や国際市場の状況について「昔では考えられなかった」と言う。Tokyo Gendai も開催当初から参加していた石井氏だが、「90年代はThe Armory Show(NY)しか出展していなかったけれど、今では年間8つのアートフェアに出展しています。」と続け、「昔はファックスや FedEx で画像が届くのを待ったり、もっとゆったりしていましたね」と懐かしんだ。現在の日本の購入者は「30万ドル(約4,700万円)未満の価格帯であれば安心して購入する」といい、特にイギリスの画家 Jadé Fadojutimi のような作家の作品は、それ以上の価格がつくこともあるそうだ。

Garrier氏と高根氏は、30~40代の若い世代のコレクター層が日本国内で台頭してきていると指摘する。Financial times 東京支局長のLeo Lewis氏は、これを「コロナ後に相次いだIPO(株式公開)の結果」と見ており、「これにより急速に若いミリオネアが誕生した」と分析している。
Garrier氏によると若い世代は自分たちと同じ世代のアーティストに惹かれているという。自身のギャラリーに所属する1980年生まれのフランス人写真家、Aurélie Pétrel が若い層を中心に世界的に人気を集めている。価格帯の手ごろさも魅力の一つであり、Tokyo Gendai 共同設立者の Magnus Renfrew 氏は「日本のアーティストは、海外の同世代と比較して手頃感がり、まだ手に入れるべき良作がある」と述べる。
だが、この状況は長く続かないかもしれない。というのも、日本の現代アーティストは続々と国際市場に登場しているからだ。最新のオークションで注目を集めているのは、1982年神奈川県生まれの画家、西村 有氏である。氏は印象的でややかすみがかったような抽象表現で知られ、2月には作品「Sandy beach(2020)」が29万6,100ドル(約4,600万円)で落札されたが、ほんの数カ月後には高さ2メートル近い作品「across the place(2023)」は、5万ドルという低い予想価格を大きく上回り40万6,400ドル(約6,300万円)で落札され、すぐにその記録を更新した。

そうこうするうちに、世界的大手ギャラリーであるDavid Zwirnerが西村氏と正式に契約を締結した。Zwirner氏いわく、自身の娘が西村の作品を紹介したことがきっかけだったという。6月のロンドンにおけるセールスシーズンでは、Sotheby’sもChristie’sも、これまで人気アーティストが名を連ねてきたトップロットに西村氏の作品設定し、どちらも事前の予想を上回る価格で落札された。また、ロンドンの有名な美術館やギャラリーにおいて、歌川 広重(大英博物館)から、現代アートの旗手・奈良 美智(Hayward Gallery)まで、日本人作家の個展が相次いで開催されている。
今後に目を向けると、日本経済は基本的に安定しているものの、パンデミック後にやや失速していることに不安の声もある。「円安は旅行者にはいいが、国内の人々には厳しい。日本に馴染みの薄かったインフレも悪影響を及ぼし始めている」とLewis氏は言い、たとえば米の価格が前年同月比で2倍になっている点を挙げる。さらに予測できない米国の関税政策の変動も、貿易摩擦への懸念を呼んでいる。
それでも、他国と比較すれば、日本は依然として魅力的な市場だ。「どの地域においても意思決定が遅くなっている。ニューヨークでのビジネスは非常に難しい状況だ。でも、我々はアジアに完ぺきなタイミングで出店できた。」とGarrier氏は言う。「若年層の購入者を育てていければ、長期予測は非常に良好であるし、彼らはとにかく若いので40年は一緒にやっていける」とも語る。Renfrew氏の中長期的な視点も似通っていおり、「日本は心理的な“憧れの地”であり、一度は訪れてみたい地である。ここ数年、日本のアーティストによる作品のクオリティの高さに多くの人が非常に感銘を受けている。これは地域や世界から人を呼ぶ大きな原動力になる。我々は一歩一歩、それを積み上げているところである」と語る。